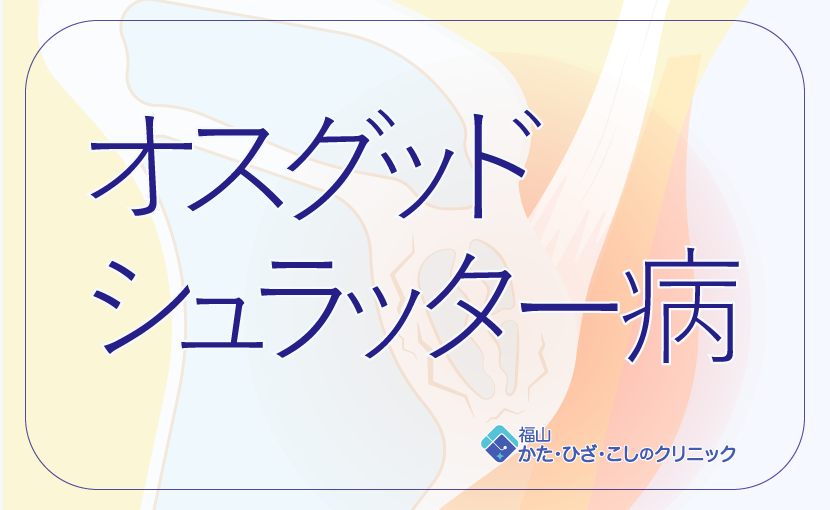1日でも早くスポーツ復帰するために
スポーツ中のオーバーユース(使いすぎ)による痛みで受診される方は少なくありません。多くの方が「いつまでに復帰できるのか」「大会に間に合うのか」といった不安を抱えています。
しかし「スポーツ復帰」とは非常に複雑で、一概に期間を断言できるものではありません。同じ病気・怪我でも、競技レベルや年齢、社会的環境によって必要な時間は大きく異なります。
ここでは、少しでも早く、そしてより良い状態で復帰するための考え方をお伝えします。
怪我の原因を考えることが第一歩
オーバーユースによる怪我は「なぜ起こったのか」を振り返ることが重要です。
- フォームの癖
- ポジションに特異的な動き(野球のピッチャー等)
- 個人個人の骨格的な特性(年齢・利き手・身長など)
これらを改善しなければ、休んで治ったように見えても再発する可能性が高いです。休養と同時にフォームや体の使い方を見直すことが確実な復帰への近道です。
コンタクトスポーツなどでの捻挫や打撲などの怪我でも、単に「たまたま」「運が悪かった」だけではありません。その怪我をするまでの過程において怪我を防ぐことができることもあります。たとえば足首の捻挫は、原因となるフォームの特徴(癖)が研究により解析されています。捻挫による痛みが改善したとしてもそのようなフォームを改善しないかぎり、同じような怪我を繰り返すことになります。
「痛み」だけでなく「違和感」に敏感になる
特にオーバーユースによる障害では痛みが出るのは実はかなり状況が悪化しているサインです。その前に必ず「違和感」や「力が入りにくい感覚」が出ているはずです。
- 「最近特定の部位が張った感じがとれない」
- 「以前と比べてスムーズに体が動かない」
- 「ダッシュやジャンプなどの記録が伸びない」
「大会が近いから」「ライバルとの競争に負けたくないから」などの社会的な要因も関連して このような状況が悪化しているサインに気が付かないことは多いです。
一度痛みが増悪して、安静を指示された時でも回復の過程において「痛みはないけれどまだ違和感がある」状態になります。その時に無理な動きをして状態を悪化させないように判断する勇気が必要です。
休養=何もしないではない
怪我をして病院にいって診断をうけ、たとえば「4週間スポーツ中止」の指示が出た場合、その間全く「完全に動かない」必要はありません。損傷した部位に負担をかけない範囲で、できることはたくさんあります。
「怪我がある状態で復帰に向けてできることはなにがあるか?」は理学療法士の専門分野です。理学療法士と相談しながらできるトレーニングをやっていきまししょう。たとえば
- 股関節や胸椎のストレッチ
- 体幹トレーニング
- 正しいフォームを意識した動作確認
などです。こうした地味で小さな積み重ねが、最終的に早い復帰を実現します。
医師が示す期間は「安全な目安」
私たち医師が「おおよそ1ヶ月は安静」と伝えるのは、安全を考えて余裕をもたせた期間です。
実際には、
- 10代の骨折と60代の骨折では回復力に大きな差がある
- 怪我からの回復は個人差や環境による差の方が大きい
のです。
よくプロ選手の報道で「医師から1ヶ月の離脱と言われたが、脅威の回復力で2週間で復帰した!」といった話がありますが、別にその選手が特異体質なわけでもなんでもありません。多分あなたが同じ怪我をしても(ちゃんと指示を守っていただければ)そんなもんです。
当院はMRI検査ができるので早期に診断がつく傾向にあり、復帰時期も早くなることが多いと思います。
医師が復帰時期を判断する基準としては局所の状態(圧痛の有無、腫脹の有無)も大事ですし、柔軟性や筋力などの身体状態も確認します。局所の状態が改善したら、スポーツ復帰を許可することはありますが、繰り返し述べているように原因となる身体的な特徴(欠点)を改善しない限りは再発するリスクが高いのでそのようなリスクについてご理解いただいた上での復帰となります。
自分の体の声に耳を傾ける
復帰の可否を最終的に判断できるのは、自分自身の体の感覚です。医師から再開の許可が出たとしても休んでいる間にどうしても身体能力は低下しています。
- 「今日はここまでできた」
- 「この動きはまだ不安がある」
といった日々の変化を感じ取り、無理のない範囲で少しずつできることを増やしていってください。
まとめ
スポーツ復帰は「完全に休む」か「すぐ全力で再開する」かの二択ではありません。
違和感を無視せず、小さなトレーニングやフォーム改善を積み重ねることで結果的に早期に、そして安全に復帰できます。
忍耐強く、自分の体の声を聞きながら地道に努力することが、1日でも早いスポーツ復帰への最短ルートです。
「大きな怪我をせずにスポーツを続けるには」とはだれもが思うことではありますが、そのためには痛みが出る前の違和感や不調に敏感になることです。そしてその違和感や不調の原因が何であるかを十分に考えることです。今現在怪我などで100%の力を出し切ってのスポーツができない状態になっているのであれば、なぜそうなったか?休まなければいけなくなる前に何か気が付かなかったか?をよく考えてみてください。
KSTRを作った理由
KSTRではそのようなスポーツ時の怪我を防止する、再発を防止するために必要なトレーニングをうけることができます。怪我を予防するトレーニングと言えば消極的に聞こえるかもしれませんが、同時にパフォーマンスを上げるためのトレーニングでもあります。クリニックでの治療が終わったあとでもトレーニングを続けていたくことによってより高い次元でのスポーツパフォーマンスができるようになっています。ぜひご活用ください。

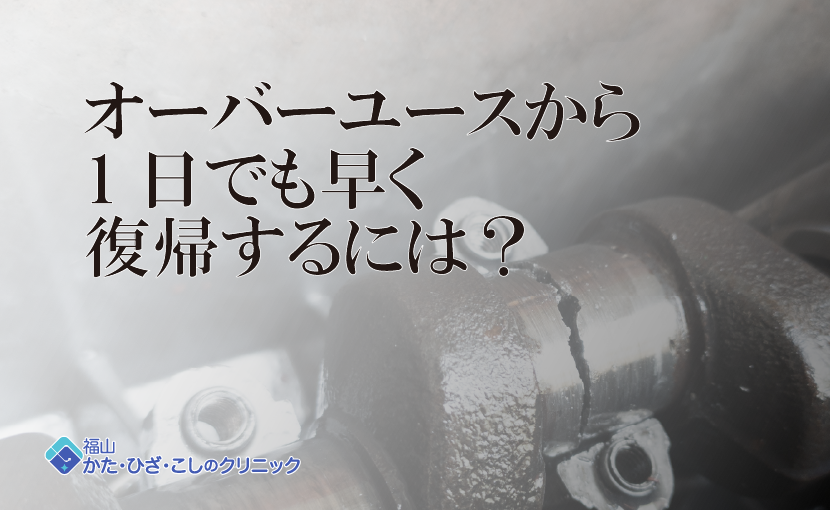
830×510-830x510.png)